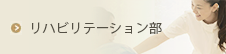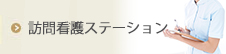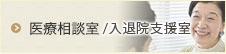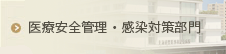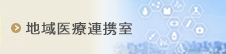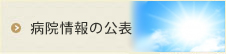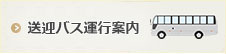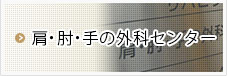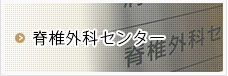リウマチ科
当科の紹介
関節が痛い、腰が痛い、全身の筋肉が痛い・・・そういった症状の場合、多くの方がまず「整形外科」を受診することと思います。しかし「関節痛=骨に異常がある」とは限らず、実は関節痛をきたす内科の疾患は多くあります。特に関節リウマチを含む「膠原病」においては、関節痛は非常に頻度が高い症状の一つです。当院は整形外科の病院ですので、関節痛で受診される方が非常に多いのですが、整形外科の疾患のみならず、関節痛をきたす内科疾患を含めて正しく診断することを一つの使命と考えて診療にあたっております。
膠原病の中には呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、消化器内科など複数の科との連携が不可欠な疾患もあります。適切な診断ののち、病状に合わせて総合病院と連携しながら診療してまいります。
関節リウマチ+
症状
治療
リウマチ性多発筋痛症+
リウマチ性多発筋痛症(polymyalgia rheumatica: PMR)は、50歳以上の高齢者に多く発症し、肩関節や股関節痛、体に近い上腕、大腿などの筋肉痛や朝のこわばり、微熱、倦怠感を呈する炎症性疾患です。「リウマチ」という名前はついていますが、関節リウマチとは別の病気です。
肩の痛みが最も頻度が多く(70~95%)、次いで頚部・臀部(50~70%)、大腿の疼痛・こわばり感がみられます。発熱・食欲不振・体重減少・倦怠感・うつ症状などを伴うこともあります。
関節リウマチとは異なり骨の破壊は診られないのが特徴ですが、膝や手の腫れ・痛みなど、関節リウマチと類似した症状を伴う場合もあり、手のむくみから10~15%に手根管症候群を呈すると言われています。
典型的には、高齢者の方が、「ある日急に両腕が肩より上に挙げられなくなって、両肩から二の腕と太ももに筋肉痛がでてきて、ももの後ろが突っ張る感じがする。特に朝に症状が強くて、着替えや寝返りが辛い」というようなものです。
この病気を診断する上で大切なことは、まず症状からこの病気を疑って、血液検査を受けることです。関節リウマチ、RS3PE症候群、脊椎関節炎、筋炎、血管炎などの他の膠原病や、頚椎歯突起周囲のピロリン酸カルシウム等の結晶沈着によっておこる偽痛風発作である軸椎歯突起症候群(crowned dens syndrome)、感染症など鑑別すべき疾患が多く、専門医の診断が必要です。
RS3PE症候群+
突然発症し、左右対称性の滑膜炎による手指や足指の関節痛、両側手背・足背の圧痕を残すむくみ、手指屈筋腱の炎症による痛みがみられる病気です。日本語の病名がなくわかりにくいのですが、remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema(自然に良くなる傾向のある、圧痕を残す浮腫を伴う血清反応陰性の対称性滑膜炎)の頭文字をとってRS3PE症候群と命名されています。
この病気と似ている病気としてリウマチ性多発筋痛症(PMR)と高齢発症の関節リウマチがあり、特にPMRで手足のむくみを伴う場合は判別が難しいことがあります。また注意すべき点として、この病気は悪性腫瘍(がん)を合併することもあり、治療とともに内科的精査をお勧めしています。
乾癬性関節炎+
乾癬性関節炎(かんせんせいかんせつえん)は、皮膚の病気である乾癬に、腫れと痛みを伴う関節炎を合併した病気です。
乾癬の皮疹は、肘や膝、頭部、殿部など刺激を受けやすい場所に多く、爪病変も多くみられます。関節症状は腫れて痛みがあるといった点ではリウマチに似ていますが、手指の第一関節に関節炎が起こりやすい点がリウマチと異なっています。また1本の指全体がソーセージのように腫れる指趾炎や、腱や靱帯が骨に付着する部位に炎症を生じる腱付着部炎がみられることがあります。仙腸関節(腰の関節)や脊椎の関節に炎症が起こると腰痛を起こしますが、炎症性腰痛と呼び、動かずにいると痛み、動かすと楽になるといった特徴があり、通常の腰痛(動かすと痛い)とは逆の現象がみられます。
関節リウマチと同様に治療が進歩している疾患であり、適切な治療によって皮疹や関節炎を改善させることが可能です。
脊椎関節炎+
脊椎関節、胸鎖関節や仙腸関節などの体軸関と手指関節などの末梢関節に炎症が生じる疾患です。脊椎関節炎(SpA)は更に、強直性脊椎炎、反応性関節炎、乾癬性関節炎、炎症性腸疾患を伴う関節炎などに分類されます。
炎症性腰背部痛(安静で軽快せず運動でむしろ改善する腰痛・背部痛)が特徴的な症状の一つです。また手指や肩などの痛みや腫れ、こわばりといった症状も伴います。炎症のため発熱、倦怠感を伴うこともあります。治療は疾患によって違いますが、生物学的製剤などでの新しい治療が進歩している疾患です。
全身性エリテマトーデス+
全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus: SLE)とは全身のさまざまな臓器に炎症や障害を起こす自己免疫疾患です。病気の原因は不明ですが、20~40歳台の女性に発症しやすいことが知られています。
症状は多彩であり、発熱、全身倦怠感などの全身症状、関節痛、皮疹、光線過敏症、脱毛、口内炎などが多くみられます。もっとも有名なのは両側の頬部と鼻に広がる皮疹で、蝶形紅斑と呼ばれます。重症の方の場合にはループス腎炎と呼ばれる腎臓の障害や神経精神症状、漿膜炎などを生じることもあります。しばしば、シェーグレン症候群や抗リン脂質抗体症候群などの他の自己免疫疾患を合併もみられます。
軽症から重症まで幅広い疾患であり、臓器障害を伴う重症例は総合病院にご紹介させて頂いております。治療はステロイドがメインでしたが、治療の進歩がみられ、免疫抑制剤や生物学的製剤の併用により予後の改善がみられている疾患です。
シェーグレン症候群+
ドライアイやドライマウスなどの乾燥症状を特徴とする全身性の自己免疫疾患で、この疾患を1933年に報告したスウェーデンの眼科医シェーグレン博士の名前から命名された疾患です。主に涙腺、唾液腺が障害されることで乾燥症状を来しますが、発熱・全身倦怠感・リンパ節腫脹・関節痛・皮疹・血球減少・間質性肺炎・間質性腎炎・末梢神経障害・脊髄炎など全身の臓器に様々な異常を引き起こすこともあります。
シェーグレン症候群はほかの膠原病との合併も多く、特に関節リウマチの患者さんでは約20%に発症するとされています。
乾燥症状、全身倦怠感、関節痛、発熱など患者さんにとっては不快な症状が多くみられますが、基本的には予後は良好な疾患です。
強皮症+
強皮症は、皮膚が硬くなる皮膚硬化を主な症状とする原因不明の病気です。限局性強皮症と全身性強皮症の2つがあり、前者は皮膚だけが障害される病気ですが、後者は皮膚だけでなく全身の様々な臓器に病変がみられる難治性の疾患です。
強皮症の病因は未だ解明されていませんが、免疫異常・線維化・血管障害の3つの異常が病態に深く関与していると考えられています。
現時点ではこの病気を根本的に制御できる治療は確立されていませんが、病気の自然経過を抑えること「疾患修飾療法」と、病気によって起こった症状を和らげる「対症療法」が行われます。
多発性筋炎・皮膚筋炎+
筋肉や皮膚、肺を中心に全身に炎症が生じる疾患で、筋力低下や筋肉痛を起こしたりするのを基本的な症状とする病気です。特徴的な皮膚症状がみられる場合を皮膚筋炎、皮膚症状を伴わない場合を多発性筋炎と呼びます。
筋症状として、太ももや二の腕、首などの身体に近い筋肉が障害されやすく、初発症状としては、しゃがんだ姿勢から立ち上がるのが困難となる、階段が昇りにくい、洗濯物を物干しにかけるのがつらい、頭を枕から持ち上げられないなどがあります。人によっては、物を飲み込みにくくなったりもします。
咳や軽い動作での息切れがある場合は肺病変(間質性肺炎)が合併している可能性があり、急速に病気が悪くなることがあるため、早期に治療が必要となります。その他、全身倦怠感・関節痛・発熱がみられることもあります。悪性腫瘍が合併する場合、体重減少・食欲不振がみられることもあります。免疫の検査として筋肉の症状が強い病型、肺病変の割合が多い病型、悪性腫瘍の合併率が多い病型など、病型によって特徴的な自己抗体が検出されることがあり、診断や治療方針の決定に有用となります。
混合性結合組織病+
混合性結合組織病(Mixed Connective Tissue Disease;以下MCTD)は、全身性エリテマトーデス様・強皮症様・多発性筋炎/皮膚筋炎様のうち2つ以上の症状が混在し、血液検査で抗U1-RNP抗体という自己抗体が陽性となる病気です。
症状は共通してみられる症状として、レイノー症状があり、その他全身性エリテマトーデス・多発性筋炎/皮膚筋炎・強皮症類似の症状が混ざって出現する混合症状、合併症があります。どのような症状が出現するかの組み合わせは個人差があります。重要な合併症として肺高血圧症があり、早期発見が必要です。
血管炎症候群+
血管炎症候群は全身に張りめぐらされている血管の壁に炎症を起こし、さまざまな臓器障害を引き起こす疾患群です。血管炎症候群は炎症を起こす血管の太さで分類されます。
大型血管(大動脈とその太い枝)に炎症を起こす疾患として、高安動脈炎・巨細胞性動脈炎、中型血管に炎症を起こす疾患として結節性多発動脈炎・川崎病、小型血管に炎症を起こす疾患として抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎・免疫複合体性小型血管炎があります。さらに、ANCA関連血管炎には顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の3つの疾患が、免疫複合体性小型血管炎には抗糸球体基底膜抗体病(抗GBM病)、クリオグロブリン血症性血管炎、IgA血管炎(Henoch-Schönlein紫斑病)、低補体血症性蕁麻疹様血管炎(抗C1q血管炎)がそれぞれ含まれます。これらの診断と治療には複数の診療科の協力が必要となることもしばしばあります。
全身症状として発熱・全身倦怠感・食思不振・体重減少・筋痛・関節痛などが出現し、不明熱の原因になります。早期診断、早期治療が予後改善に有用です。
成人スティル病+
成人スティル病は、発熱・皮疹・関節症状を主な症状とする全身性の炎症疾患です。発熱に伴って皮疹や関節痛がみられ、解熱とともに皮疹、関節痛が消失するという症状が特徴的です。診断の決め手となる症状、検査所見が乏しいため、症状や所見から総合的に診断をします。小児におこるスティル病(全身型若年性特発性関節炎)と同様の病像が成人(16歳以上)に起こったものと考えられています。
一般的に20~40歳代の比較的若い成人が発症しますが、最近では65歳以上での発症例も増えています。基本的には生命予後の良い病気ですが、半数の患者さんが寛解(症状のない状態)と再燃(再び病状が悪化する)を繰り返します。時に、播種性血管内凝固症候群(DIC)や血球貪食症候群と呼ばれる重症な病態を合併することもあり、注意が必要です。
ベーチェット病+
ベーチェット病は、口腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部の潰瘍、皮膚症状、眼症状を主症状とする全身の炎症性疾患で、時には腸管や血管、神経も障害されることがあります。トルコの眼科医ベーチェットが最初に報告したことからこの名前が付けられました。症状を繰り返すのがこの病気の特徴ですが、眼病変は失明の原因となり、腸管、血管、神経の病変は生命にかかわることもあるので、注意が必要です。
ベーチェット病の原因は現在も明らかではありませんが、発症には遺伝素因と、環境要因の両方が関与するとされています。遺伝素因の一つとして、ヒト白血球抗原(HLA)の中でHLA-B51というタイプを持っていることは、ベーチェット病発症のリスク因子の一つとして考えられています。
再発性多発軟骨炎+
再発性多発軟骨炎(relapsing polychondritis:RP)は全身の軟骨組織に炎症が起こる疾患です。耳・鼻・目・関節・気管・心臓・血管などの軟骨組織やコラーゲンを多く含む組織に様々な症状が起こります。発症早期の診断が難しく、軟骨の破壊が進み、耳介軟骨の変形や鞍鼻(鼻の付け根がへこむ状態)になってから診断されることも多いです。原因はまだよくわかっていませんが、コラーゲンに対する自己免疫学的機序が考えられています。炎症は再燃と軽快を繰り返しながら次第に進行し、命にかかわるような臓器障害を残すことがあります。特に気道病変は死因の10~50%を占める重大な病変であり、早期の診断治療が必要です。
痛風・偽痛風+
■痛風(gout)
代表的には足の親指(母趾基関節など)の付け根などの下肢の関節の1か所に関節炎を起こすことが特徴です。歩くことが困難なほどの痛みと腫れ、熱感を自覚して、炎症をおこしている関節は赤く腫れ上がります。一般的には7~10日で自然に改善して、次の発作が起きるまでは全く無症状です。高尿酸血症を放置してしまうと、関節炎を起こす頻度が上がり、多数の関節に痛みが出るようになります。発作時は炎症を抑える治療を行いますが、高尿酸血症の治療を行い尿酸値を下げる治療を継続することが必要です。
■偽痛風
痛風では圧倒的に男性に多く罹患するのに対して、この病気では男女差がありません。変形性関節症という加齢に伴った関節の変形が最も重要な要因と考えられていますが、55歳以下の比較的若い年齢の方では、遺伝性疾患、代謝性疾患(副甲状腺機能亢進症、低マグネシウム血症、低リン血症)などが偽痛風の原因として隠れていることがありますので、血液検査や画像検査が必要になることもあります。また、膝の半月板を切除した後の膝関節に偽痛風がみられることがあり、外傷や手術との関連性も知られています。
自己炎症疾患+
全身性の炎症を繰り返す疾患で、繰り返す発熱と、ときに関節・皮膚・腸・眼などの病変を伴う疾患群です。家族性地中海熱(familial Mediterranean fever: FMF)が代表的な疾患で、その他TNF受容体関連周期性症候群(TNF receptor-associated periodic syndrome: TRAPS)、クリオピリン関連周期性症候群(cryopyrin-associated periodic syndrome: CAPS)など多くの自己炎症性疾患があります。
代表的な疾患である家族的地中海熱では、周期性発熱が高頻度にみられます。発熱の期間は1~3日と短く、自然に軽快します。発熱に伴い関節炎・皮疹などの症状がみられるほか、漿膜炎を来たし、胸膜炎では背部痛、腹膜炎では腹痛を伴うことがあります。発熱発作時に血液検査をすると、白血球増加、高値の炎症反応がみられますが、数日で発熱、炎症反応ともに消失するので、風邪や腸炎、尿路感染症などと診断されていることも少なくありません。しかし炎症を繰り返すとアミロイドーシスの合併がみられることがあり、診断と治療により症状と予後の改善が期待できる疾患です。不明熱の重要な鑑別診断の一つです。
免疫チェックポイント抗体治療に伴う筋骨格症状+
irAEとは免疫関連副作用(immune-related Adverse Events)のことで、おもに免疫チェックポイント阻害薬の投与により引き起こされる副作用を指します。免疫チェックポイント阻害剤は、免疫を抑制する分子を阻害することで、がん細胞に対する免疫を増強させて治療効果を発揮します。しかし、免疫チェックポイント阻害薬は、がんに対する免疫だけを選択的に増強することはできず、免疫全般を過剰に活性化してしまい、免疫が自分自身を攻撃してしまうといった様々な自己免疫疾患を引き起こします。症状として、間質性肺疾患、大腸炎、甲状腺機能低下症、下垂体炎、糖尿病、末梢神経障害などがありますが、関節炎や筋症状も比較的多くみられます。癌治療がうまくいっているほど副作用が起きやすいことが知られており、腫瘍内科医と相談して治療を進めます。